花粉が飛ばない沖縄へ 🛫
筆者はとにかく酷い花粉症の持ち主です。
特に春先のスギとヒノキの花粉には、長年来、悩まされていました。
そんな花粉症から逃れることができたのは、今からちょうど10年ほど前、テレビだったか週刊誌だったかで「杉花粉から逃れたければ、花粉のない処に行けばよい。沖縄とか北海道はそもそもスギもヒノキも植わっておらず、花粉がないよ。」と言う記事を知り、「なるほど。では、この時期、北海道は寒いから沖縄だ。」と思い立ち、さっそくその年の3月下旬に、人生初めての沖縄旅行。
3泊4日の日程でしたが、実験的な試みで那覇市内に滞在しました。
もちろん、沖縄にいる間はクシャミもなく、本当に地獄に仏とはこのことか!と、嬉しくなり、来年からはせめて一か月間、沖縄で過ごそうと決め、3日間の滞在中は観光そこのけで那覇市内をあちこち廻り、安くて快適そうな宿探しに明け暮れました。
おかげさまで、ひと月を10万円足らずで過ごせる快適な宿が那覇市内に見つかり、次の年からは毎年、那覇市を中心に沖縄滞在を続けています。
もっとも、2021年と22年はコロナの影響で、旅行ができずに我慢の年でしたが、今年2023年、3年ぶりに訪問。
2月末から4月下旬までの二か月間、花粉を忘れて久しぶりの沖縄生活をエンジョイしました。

これからも普段は節約に努め、花粉の季節は
沖縄で過ごそうと計画しています!
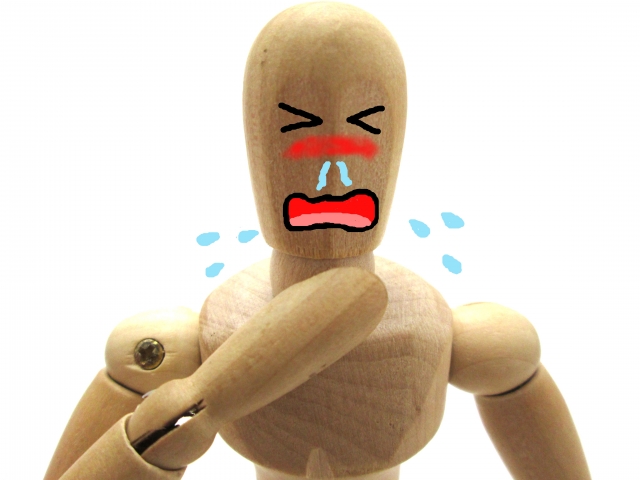


沖縄諸島はこのようにして誕生した
今回はその中でも、沖縄本島を中心とする沖縄諸島がどのようにして誕生したのか。調べた限りの情報を書いてみたいと思います。
日本列島の誕生については、このブログの「逆さ地図」でも簡単に述べましたが、約3千万年ほど昔に、厚さ100kmもある重い太平洋プレートが、徐々に沈み込み始めるとともに、ユーラシア大陸の東端が引きちぎられるように離れ、日本列島の原型となりました。

その中でも九州〜沖縄を含む西日本には、南側からのフィリピン海プレートが沈みつつある太平洋プレートの補完のような形で押し寄せましたが、本州の中部から九州に掛けては熱いマグマの層が地下に潜り込み、その塊がカルデラ状に地上に噴出。とんでもないエネルギーとなって広範囲で噴火しました。
今も残る典型的な例が阿蘇山のカルデラ地帯ですね。
また、鹿児島の南方に浮かぶ屋久島も、冷えたマグマの塊である花崗岩が隆起してできた島と言われています。マグマが冷えて出来る花崗岩は周囲に比べ比重が軽く、年月をかけて上に動くとともに、地表の殻が押し上げられて現在のような山系になるとのことです。

一方、九州より南方の沖縄諸島地域は、熱いマグマの層でなく、同じフィリピン海プレートですが、冷えた部分の層が地下に潜り込み、その為に火山帯は生じることなく、実に2億年も前から大陸との離合集散を繰り返しました。
500万年ほど前には琉球列島と大陸の間に島尻海(しまじりうみ)と呼ばれる海域ができ、200万年前から現在に掛けて大陸との大きな裂け目となる、深い沖縄トラフが形成されました。
大陸と沖縄本島等の琉球列島の北側の島々との間で、列島に近いところに水深の深い沖縄トラフが横たわっています。
そして40万年前から氷河期の終期である2万年前まで、南琉球地域は大陸と陸続きとなったりしていましたが、氷河期が終って海面が上昇し、陸地が狭くなり、9500年前にはサンゴ礁が隆起して、現在の琉球列島の原型ができたと言われています。

因みに、日本で最も古い人の遺骨と言われれている2万年前の沖縄本島の湊川人は、このような地形の変動の中を大陸から島伝いに渡来してきた人々と考えられています。
また、イリオモテヤマネコやハブ、ヤンバルクイナなど氷河期の時代に、陸続きの大陸から移動してきた動植物が、その後大陸と切り離されて孤立した環境のなかで、独特の生態系を形成しました。

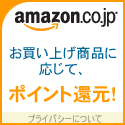
「沖縄物語」シリーズを始めます











コメント